イワノサンゴクシ
1 三国志城跡地 |
 |
||||
| まさかの通行止め!! | 路肩が崩れております | 反対側から見ても通行止 | 通行止めを食らった位置 ここからぐる〜っと歩いて登る |
||
| ここを降りると南水門 | コンクリの廃墟がありました こういう近代人工物は 中に人がいそうで怖いな |
いわれなければ 「南水門」だとは分からない |
南水門 | 奥に礫が連なっている箇所があり、 不自然に立っている石がありました 何かの石碑でしょうか?? |
||
| 大師堂 | 脇のお地蔵様 | 神籠石サミット開催記念植樹 | |||
| 石城山神籠石の案内 | 第二奇兵隊施設の案内 | パンフレット | |||
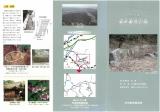 |
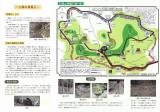 |
 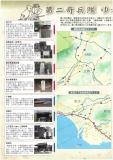    |
|||
| 神籠石のパンフ | 第二奇兵隊のパンフ | ||||
| 神籠石の解説 | 随身門(旧仁王門)の解説 | 随身門 | 随身様 | 門から先を見る | 逆側から随身門 | |
| 仁王門から神護寺へ 向かう参道 |
右手は谷です | 石城神社解説 | 鳥居 | 拝殿と本殿。本殿や拝殿の屋根が幣殿の屋根にくっついてるように見えますが 時代的にどういう順番でつくられたのでしょうか |
||
| 須賀社 | 岸信介氏による七言絶句 | 明治維新百年記念 | 神護寺跡解説 | 第二奇兵隊本陣跡解説 | ||
| 広々とした本陣跡 | 奥には千手観音 解説には「獅子の穴」が載ってますが、 載ってることに気付いたのは今(2021年)です |
先へ進む | ||||
| 眼下に凄いのが見えてきました | 接近します | ここから降りてきました | ||||
| いくつかの石をアップで。下に若干の水気がありましたが…… | ||||||
| 上流部から水門側へぐるっと見る | ここからの眺め | 逆側から見る西水門 | ||||
| 眼下に広がる景色 | 下におりました | 右手の石垣 | ここから降りてきた | |||
| 90度の折れ目の水の流れ | 向かって正面の石垣 | アップで | |||
| 排水口 | 奥にフラッシュを焚いてみた | あらためて石垣を見る | 見下ろします | ||
| こんな道を進みます 右下に石が並びます |
龍石 | |
| 北門 | 列石の様子 | ここの解説板は 北門でなく神籠石の解説 |
この段組の上に 門があったのでしょうか? |
角っこの沓石 | ここに門があったのか? | |
| 沓石 | ちょっと上から見下ろす なぜもうちょっと上に 登らなかったのかは 覚えておりません |
北門跡のようす | 下段の石垣もしっかりしています | |||
| 瀬戸内海 | 北部九州 | |
|---|---|---|
| 列石の加工方法 | 割石ないし一部切石 | 切石 |
| 列石の配置方法 | 列石の非露出(土塁に覆われている) | 列石の露出 |
| 道路 | 道路脇の列石 列石前にくぼみがあり、てっきり水はけのためかと思ってましたが もしかしたら土塁部分を撤去 |
解説 | 土塁が露出している? | |
| 石垣が登場します | 東水門! | |||||
| 水が流れています | 排水口 | フラッシュ焚いてみた | 逆側からみる東水門 | 石垣 | さらば東水門 | |
| 正面方向 | 石垣がありますが…… | 解説 これを先に読めばよかった |
修理事業の名残の石垣、ということになります。 | 振り返ります | ||||
| ぶれたけれど、鳥居 | 神護寺の宿坊東坊跡にのこるお地蔵様と石塔 | 五十猛神社 「いたける」と読みます。 検索した限り「五十猛」と書いて「いそたけ」と読むのが一般 (ATOKさんも「いそたけ」から「五十猛」に一発変換できます) 島根には五十猛神が上陸した五十猛町があるようです |
||||
| 物部神社 | さらに鳥居があります | 蜘蛛の巣トラップがあります | ||||
| 葦原神社 | 石城島神社 | 若宮神社 | ||||
| 日本神社 | さざれ石 | 四季桜 | |||
| 磐山神社 | 宇和奈利社 | |