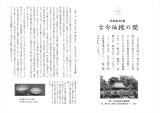クマノスイゼン
2.水前寺成趣園
2.1 入園
いよいよやってきました。ニワカ庭園マニアとして、以前からもちろん知っていたお庭ですが、熊本競輪場の近くにあるがゆえに熊本競輪とセットで行こうと思っており、熊本競輪に行くタイミングが無かったのでここに行くタイミングもなかなかつくることが出来ませんでした。
そんなわけで、かなりワクワクな気持ちで乗り込んだのであります。
ところで。ワクワクしていたとか調子のいいことを書いておりますが、「水前寺成趣園」って読めますか。水前寺はいいとして、問題は「成趣園」。自分の中では、「せいしゅえん」と「じょうじゅえん」の2択でして、どちらかというと心の中では「せいしゅえん」とつぶやいていることの方が多かったです。まあ、人様に向かって「水前寺成趣園」とつぶやくことはないので、特に真剣に気にしたことが無かった、というのが正直なところです。この混乱の原因の1つは、私が使っているATOK君が「せいしゅえん」「じょうじゅえん」のどちらでも「水前寺成趣園」を出してくれなかったことにも起因します。徳島県民は熊本に恨みでもあるのか。
まあ結論としては、「すいぜんじじょうじゅえん」が正解です。ATOKが変換してくれないので2択以外の第3の答えがあるのでは、と危惧してましたが、そうではありませんでした。
とまあ、ごたくはさておき、いざ水前寺成趣園。出水神社の鳥居が入場口に立っているので、お庭と神社はほぼセットなのでしょう。このあたりの細かい歴史や由緒はおいおい見ればよい。
観光地らしく、参道の脇をお土産屋さんが堅めます。道のど真ん中はくまモンがガードしており、仮にここが出水神社の参道だとするならば、愛知でよく見た蕃塀的な感じでしょうか。
では、入園。とりあえず園内地図を片手に、移動経路を考えます。
 |
 |
 |
 |
 |
| 石標 |
パンフレット |
園内地図 |
ここも水遺産 |
 |
 |
 |
 |
|
| 明治天皇御臨幸碑 |
園内にも売店が並びます |
解説板
木の本数は他言語に訳されておりません |
|
2.2 古今伝授の間
まずは入って正面の、ここから。あとで行こうとすると、競輪の時間が迫ったりなんだりして行くのを忘れそうだ。
そして、ここにきて、あらためてここが細川さんのお庭であることを思い出しました。古今伝授といえば、細川藤孝でしか知りません。細川さんがこれで関ヶ原の難を逃れたことはおそらく日本国民の共通の知識だと思いますが、ぶっちゃけ「古今和歌集の解釈が代々秘伝として受け継がれている」という以上の知識はありませんし、実際に受け継いだ人は細川幽斎藤孝しか知りません。古今和歌集以外の勅撰和歌集以外にもこのような秘伝の解釈学があるのかも知りません。その程度の知識なのですが、この「古今伝授」という四字熟語を見るとなんかワクワクしてしまう自分がおります。秘伝の書みたいな雰囲気があるのがいいんですかね?
Wikipediaを見ると、系統は3つに分かれており、うち2つは今も残っているとのことです。現代人からしてみると、そうまでして秘密にしなければならない解釈学とはなんなのか、というのが気になるところですが、まあそれも含めて浪漫がありますな。
古今伝授はいいとして、「古今伝授の間」とはなんぞや。細川藩がここにやってきたのは加藤藩が潰されたからなので、細川幽斎がここで古今伝授をやったとは思えません。
というわけで、読みやすくなっていた解説その2を読みます。パッと検索して出てきたこちらも参照。
解説その2によると、この古今伝授の間というのはもともと八篠宮智仁親王の学問所として京都御所内にあり、のちに細川幽斎が智仁親王に古今伝授をおこなったのがまさにこの古今伝授の間だとのこと。
ちなみに、この智仁親王、おそらく八条宮智仁親王のことだと思うのですが、八条宮智仁親王のWikipediaでは「八篠宮」というワードは出てきません。Wikipediaの桂宮家の項でも、八条宮から桂宮になった流れがわかりますが、「八篠宮」というワードは出てきません。ううむ、篠と条、字が似ているだけに略字的な何かだったりするのだろうか。というか、単に「八條宮」と書くべきところを「八篠宮」と書いただけじゃないかという気がしてきたぞ。
ところで。「ともひとしんのう」という名前を聞くと、おそらくほとんどの日本人が多い浮かべるのは我らが寛仁親王(寛の字の変換は一旦忘れてください)。今なお競輪界に名前を残されている偉大な人物です。こうして古今伝授の縁で「ともひと」様の建物がここ熊本にのこり、そこから近いところにある競輪場ではともひと親王牌の車券を買うことが出来るわけです。だからどうした。
 |
 |
 |
 |
 |
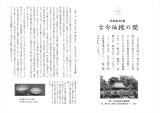 |
 |
| 古今伝授の間入口 |
解説 |
解説その2 |
解説その2のアップ |
パンフレット |
てなわけで、古今伝授の間へと入ります。敷地内には噂の建物があり、その前庭には誰でも入ることが出来ます。そして、そこからの景色は素晴らしい。いや〜、絶景絶景。ここでごろ寝したら気持ちよさそうだぞ。こんな景色があったら勉強しなくなるのじゃなかろうか。
なお、古今伝授の間コーナーには最初に入り、最後にあらためて入りなおしております。面倒なのでここに写真を固めてしまおう。
あらためて入り直した際には解説ボランティアの方がおられて(別の人に向けて)解説をしておられました。おそらくこの茶室の窓についてなにか解説されていて、私はそれを盗み聞きしたはずなのですが、メモが残されていません。ううむ、なぜ残さなかったのだろう……。
 |
 |
 |
 |
 |
| 入ります |
進みます |
振り返る |
古今伝授の間 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 建物と前庭 |
窓 |
南側 |
そしてここの景色は本当に素晴らしい。
 |
 |
 |
 |
| パノラマ |
|
ぐるりと |
 |
 |
 |
 |
 |
| あらためてぐるりと |
水面 |
 |
 |
 |
 |
|
| ちょっと移動して、ぐるりと |
いろんな批判を
浴びてそうなビル |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 古今伝授の間の前庭から撮った写真後半戦 |
では、ここから右回りに池のまわりを回ります。ちなみに、普段「右回り」「左回り」という表現になれていると、突然「時計回り」と言われてどっちか戸惑ってしまうのは私だけでしょうか。
それにしても、古今伝授の間から見たときにも思いましたが、この水前寺成趣園、とにかく築山が美しい。いや〜絶景絶景。
というわけで、まずは正面広場からの眺め。
 |
 |
 |
 |
| ぐるり |
パノラマ |
|
 |
 |
 |
 |
|
| ちょっと移動 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 水も綺麗です |
亀かと思ったら石だった |
鯉のエサを鳩が食べる |
石橋を渡りながら、出水神社に接近します。
2.3 出水神社
出水神社に参拝します。
この出水神社、解説板によると創建は明治11年、1978年ですから、西南戦争の数年後。旧熊本藩士が藩主に思いをはせて創建したようです。
細川幽斎から連なる歴代細川家当主と、細川ガラシャ夫人が祀られているとのこと。どうして唐突にガラシャ夫人だけが出てくるのか、西南戦争なり明治維新なりそれ以外の何かなりで奮戦しあるいは犠牲になった藩主夫人はいないのか、部外者的には気になるところではありますが、創建した方々がそれでいいと言ったのだからそれでいいのであります。
ここ出水神社は、庭園内にあるとは思えない、非常にしっかりとした神社であります。さすが、細川家歴代当主を祀っているだけのことはあります。細川家というと、私のようなミスターシービー世代の人間は細川家第18代当主にして第79代内閣総理大臣の細川護熙氏を思い浮かべてしまいますが、彼に関するものは何も無さそうでした……と思ってたら、鳥居に名前が登場。そりゃそうよね。ちなみに、水前寺成趣園まつりにて陶芸家細川護熙氏の作品展示がおこなわれたりもしているようです。
 |
 |
 |
 |
| 鳥居 |
境内 |
拝殿 |
 |
 |
 |
 |
夏目漱石句碑
しめ縄や 春の水湧く 水前寺 |
神水 長寿の水 |
 |
 |
 |
 |
| 光復 |
|
五葉の松 |
宗不旱歌碑 |
 |
 |
 |
 |
| 昭和天皇御手播の松 |
鳥居越しに見る庭園 |
扁額は細川護熙氏によります |
参拝を終え、再び園内散策に復帰。
今度は、先程来見てきた山へと進んでいくことになります。池沿いが見返り通り、神社側の道が神社通りと名付けられているようです。見返り通りは階段になっているので、乳母車や車いすの人はきつそうですが、私のようなボッチおじさんは池沿いを歩きたくなりますよね……
スイゼンジノリ。どれが海苔なのかはよく分からず。
あらためて、入江を見たり、築山を見たり。この築山、阿蘇山のイメージなのかと思ったら、富士築山という名称がついておりました。ここまできてもやはり富士山なのですな。
2.4 稲荷神社
続いて稲荷神社。扱いとしては出水神社の境内社という扱いのようです。
で、裏手側、というか東側をぶらぶら歩きます。
 |
 |
 |
 |
 |
| 長岡護全公銅像跡 |
細川忠利公、幽斎公銅像 |
 |
 |
 |
 |
|
| 東側から眺める富士築山 |
東通り |
東通りから眺める富士築山 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 肥後六花 |
肥後芍薬 |
肥後菊 |
 |
 |
 |
 |
 |
流鏑馬の馬場
細川家は武田流だとのこと |
縁結びの木 梛 |
2.5 裏富士
富士築山、池側、古今伝授の間側から見ると非常になめらかな山で、美しいものでした。
ところが東側から見ると、芝が四角く刈り取られていたり、木が植えられていたりと、滑らかさを欠くものになっております。これ、さすがに意図的にやっていると思いますし、やるからにはおそらく富士山の名所を意識しているのだと思います。が、富士山については素人なので、これらが何を表しているのかは私には分からないのでありました。
また、こちらのサイトによるとこの築山は西南戦争において頂上が削られ、政府軍の砲台が築かれたとのことです。そりゃまあ戦争において庭園の風情を気にする余裕なんてあるわけないです。とりあえず、平和に庭園を闊歩できる時代に生きた幸せかみしめることとします。
 |
 |
 |
 |
 |
| 裏富士 |
麓の芝 |
 |
 |
 |
 |
|
| 細川桜 |
|
ポコポコした丘と綺麗な芝生 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 丘越しに富士築山を見る |
ポコポコした丘 |
富士築山も素晴らしいですが、そのまわりのポコポコした丘も素晴らしいですね。なんといっても素晴らしいのがこの滑らかな芝の姿。芝生を維持されている方々には頭が下がります。
そこから、湖畔通りを下って湖に出て行きます。
そういえばさっきまでこの水のことを「池」と読んでましたが(まあ一応池泉回遊式っていうし)、湖畔通りがあるからには「湖」と呼ぶべきなのだろう、ということで、突然ここから湖と呼び始めることにします。
 |
 |
 |
 |
 |
| 湖畔通りを進みます |
振り返りながら丘を眺める |
古今伝授の間が見えてきた |
湖に出ました |
 |
 |
 |
 |
 |
| 湖を眺めます |
能楽殿 |
水門方向は、時期が時期ならば花菖蒲が咲く場所のはずです。こちらが加勢川に繋がり、そこから取水しているのではないかと思います。
 |
 |
 |
 |
 |
| 肥後花菖蒲が咲くはず |
南側から北方向を望む |
|
南側通路と、ここにも水門 |
 |
 |
 |
 |
|
| 移動しながら湖と築山方向を眺める |
|
このあと、再度古今伝授の間を眺めたのはすでに書いたとおりです。
天気がよかったこともありますが、とにかく湖と築山のバランスが素晴らしい庭園でした。
昨今はオーバーツーリズムだのなんだのかんだの言われておりますが、こちらは来園者が少なく、まあ自分は少ない方が居心地はいいものの、これで大丈夫なのか不安にはなってしまいます。
まあ、そのあたりは熊本市に考えて貰うとして、いよいよ競輪場へと向かいます。
熊本市街地 → 水前寺成趣園 → 熊本競輪 → 八女その1・その2 → 岩戸山古墳
旅行記TOP / テーマ別