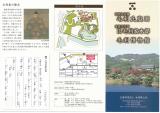
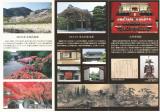


メイショウモウリ
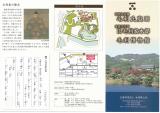 |
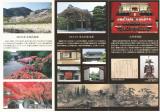 |
 |
 |
| パンフレット | 防府市観光案内 | 案内図 | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 入ります | 庭園側の廊下 | 縁側 | 縁側から庭園を見る | 重要文化財です | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 大広間(客室) | 百万一心について | 天井の格子 | |||
 |
 |
 |
 |
| 狩野探幽の鳳凰図の複製 応接室にあったはずなのだけれど、 なぜ応接室の写真それ自体がないのか不明です |
中庭側の廊下 右手は大広間 |
トイレ | |
 |
 |
 |
 |
| 中庭 | |||
 |
 |
 |
 |
| 階段 | 階段をのぼったところ | ||
 |
 |
 |
 |
| 大広間 | 大広間から庭方向 | ||
 |
 |
 |
 |
| 庭沿いの廊下と縁側 | 庭をのぞむ こちらの方が綺麗 |
中庭を見下ろす 中庭は1階の方がいいですね |
|
 |
 |
||
| 水屋。なんでフラッシュ焚かなかったんだろうか | |||
 |
 |
 |
 |
 |
| 特別公開 | 中庭側の廊下 | 庭へ向かう廊下 | ここの眺めはいい感じです | |
 |
 |
 |
 |
| 公居間 | 大正天皇のあとにくるのは 句点でなく読点だと思う |
左 | 右奥 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 御上用厠 一般人向けと何が違うのだろう |
中庭 | 廊下 | ||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 洗面所 | 奥浴室 | |||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 玄関外 | 武将隊 | 本日のおもてなし | 解説板 | こちらは別の撮影だと思います | |
 |
 |
 |
| 解説 | 入っていきます | 真っ直ぐ |
 |
 |
 |
 |
| 庭側から本邸を見る | |||
 |
 |
 |
 |
| 本邸まわりの眺め。白いのは博物館かな? | |||
 |
 |
 |
 |
 |
| 水の流れ | 築山 | 石塔 | ||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 池に出ました | 歩き出します | 遠くに毛利氏邸と石橋 | 石組みも気になります | ||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 対岸から石組みを眺める | 石橋と毛利邸を上手く撮ろうと移動しながら撮影している図 | 角度を変えて池を眺める | |||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 小川 | 河口の飛び石 | 河口の石と石橋と四阿と池を撮ろうとした図 | |||
 |
 |
 |
 |
||
| 浜 | 浜越しのいけ | 角度を変えて池を撮る | |||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 池越しに石組みを見る | 毛利氏邸方向をぐるっと。意味もなく縦に撮ったりもしてみる | ||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ひょうたん池 | あずまや | 石橋 | 石橋越しに毛利氏邸 | ||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 逆側から | 反対側から石橋を | 水が落ちてます | あらためて毛利氏邸 | 門 | |
 |
 |
 |
 |
| 行き場を失った配布物。「侯爵毛利邸の100年」より | |||
 |
 |
 |
 |
| 防府のゆるキャラだと思われます | 国衙の北側にある解説板 | 北側から南方向を見る | |
 |
 |
 |
 |
| 南側から北を見る | 意味ありげに芝が生えていない場所があります | ||
 |
 |
 |
 |
|
| 国衙の碑 | そのあたりから北方向 | 椿が咲くようです | ||
 |
 |
 |
 |
|
| 「国庁」の碑と国庁寺 | 国庁の碑 | 国庁寺境内図 | 国庁碑 | |
 |
 |
 |
 |
 |
| 国庁の保存 | 国庁のしくみと仕事 | |||
 |
 |
 |
 |
 |
| 史跡周防国衙跡 | 周防国衙跡 | 周防国衙跡 | ||
 |
 |
 |
 |
| 発掘調査中 | |||
 |
 |
 |
 |
 |
| 気になる案内 | 到着 | 解説板 | 馬神様 | |
 |
 |
 |
 |
 |
| 中を覗かせていただきました | 藁の馬が供えられておりますが、供えた方は咳や風邪のために供えたのか、男性を強くするために供えたのか、どちらなのでしょう | |||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 天満屋 2階3階の窓枠に味があります |
花の妖精ぶっちーというらしい | ういろう豆知識 | たぶんここだけ というコーヒーういろう 正直でよろしい |
セルビアの男女バレーチームの ホストタウンだったようです |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 山門 | 解説 | 本堂 | |
 |
 |
 |
 |
| 中。赤いです 三十三観音は 中に収められてるのかな? |
中が赤いだけに 車も赤い |
石像 | 入口の観音様 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 防予フェリー | 柳井競馬・オート跡地 | 柳井散策 | 防府天神 | 防府競輪 | 防府天神 | 周防国分寺 鐘栄稲荷 |
毛利氏邸 毛利氏庭園 |
防予フェリー |
| 三津→柳井 | 柳井 | 防府 | 柳井→三津 | |||||