いきなりトリニダードトバゴの競馬の話から始まる本。途中、ギリシャ古式競馬やイギリスの話なども挟まれる(正直イギリスブックメーカーの話は蛇足に思えた)が、メインは日本の中央競馬。地方競馬の話題は大月隆寛にボールを投げている。
正直、私には文化人類学についての知見が皆無で、文化人類学的な物事の切り方というのがよく分からないし、それがこの本でどこまで成功しているのかも分からない。
読んだ感じは、競馬の構成要素や予想のあり方について分析的な記述があったのだが、文化人類学からみた競馬という意味でこれが成功しているのかは分からない。
文化人類学云々を除けば、学者が競馬について熱く語っている本、という感じ。1988年の競馬の空気感(客層の若年齢化、女性の参加、ジャパンカップへの考え方、馬複導入と射幸性の問題)を感じられておじさん的には楽しい本であった。
難しいことを考えず、1988年に、岩波新書というお堅い新書で競馬が語られた、しかも一頭一枠制について熱く語っているというあたりが重要なのかな。
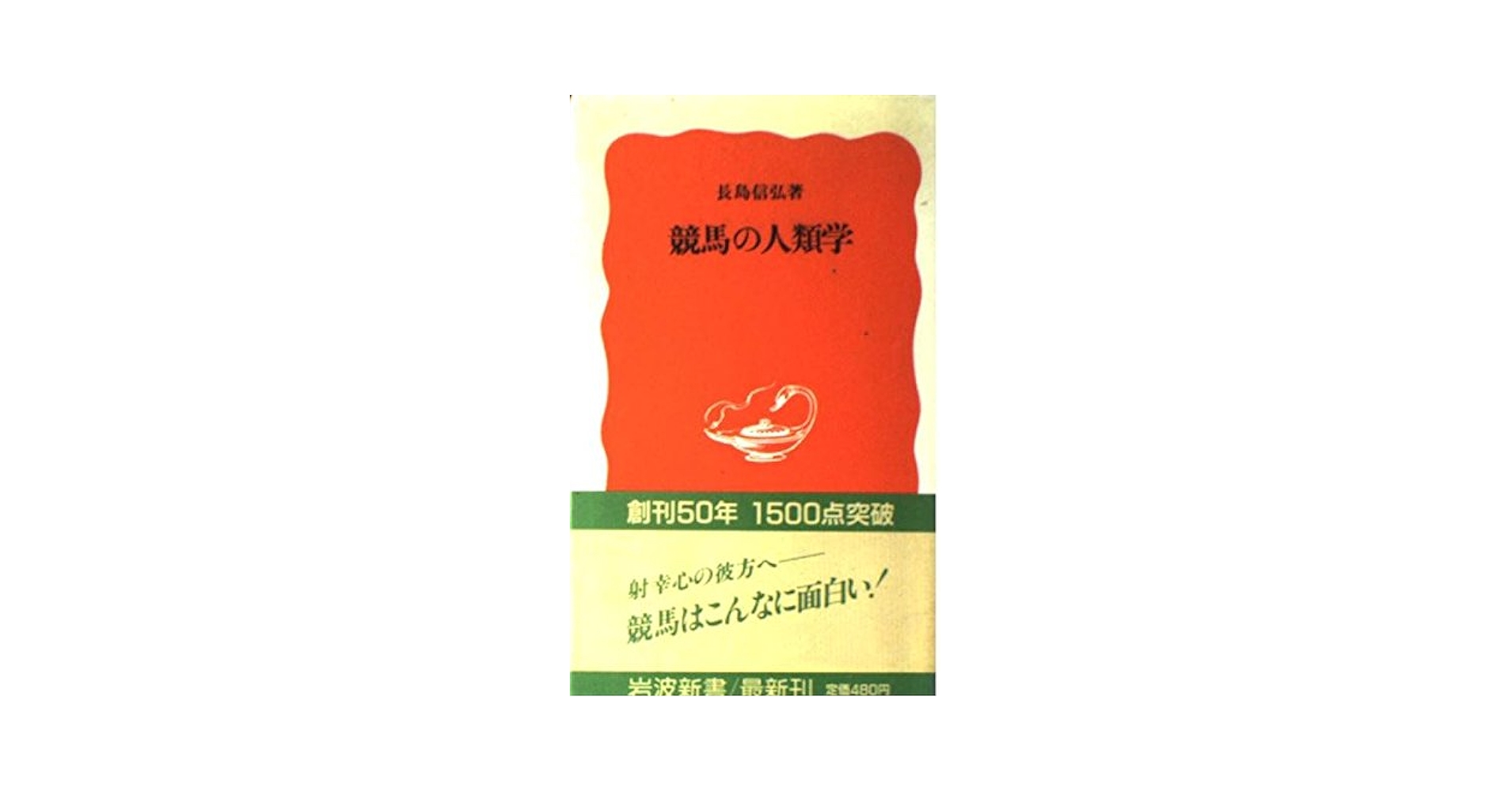
競馬の人類学 (岩波新書 新赤版 17)
競馬の人類学 (岩波新書 新赤版 17)



コメント